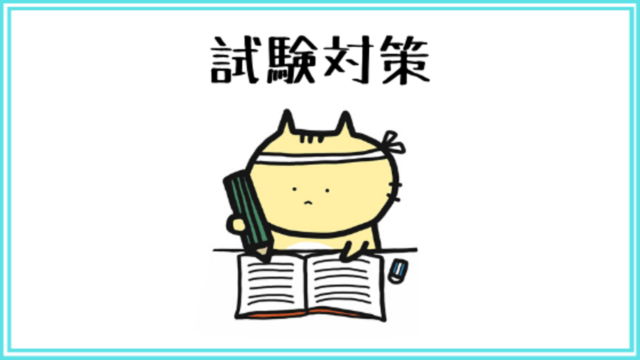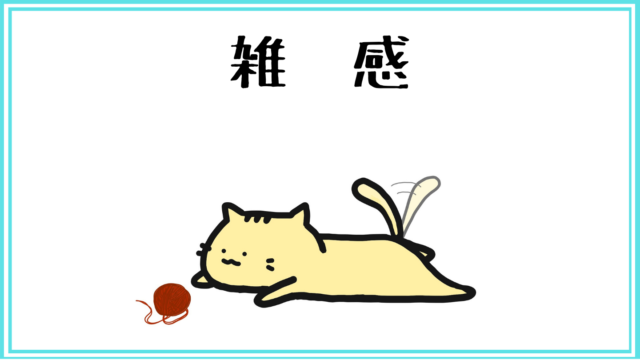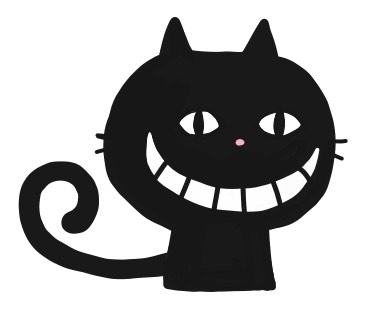こんにちは、ねこきん(@nekokin37)です!
2回に渡って答案構成の必要性とやり方を書いていきます!
今回は『答案構成の必要性』と『答案構成のためのインプット』についてです。
論文試験を受けたことがない人は、初めて過去問とかの解答例をみたとき『ホンマにこんな解答を書けるようになるんか…?』と感じると思います(少なくとも私はそうでした)。
大丈夫です。
答案構成をして、書く訓練をしていけば少しずつ書けるようになってきます。
一回、答練で6割くらい取れると自信につながって勉強自体も楽しくなってきますよ!


答案構成とは『答案の道筋』を作ること
答案構成とは『答案の道筋』を作り上げることです。
- 問われている論点を抽出する
- 論点に対応する”解”を見つける・考える。
- 解答の各順番決める(=解答骨子の作成)。
これが答案構成です。
答案構成をしないと、論文を解く力はつきません。
答案構成の必要性
なぜ答案構成をする必要があるのか、具体的に見ていきましょう。
論点を抽出するため
答案構成最大の目的は論点を発見することです。
論点、すなわち”問われていること”がわからないと、何を解答として書けばいいかもわかりません。
問われていることがコレ(論点抽出)、それに対する解答はコレ、という風に当てはめをしていく作業になります。
解答の流れをキレイにするため
解答には流れがあります。
答案構成で『論点の抽出し、解答骨子を作る』作業をしていないと流れがぐちゃぐちゃで読みにくい答案、つまり”点が乗りにくい”答案になってしまいます。
例えば、『上位概念 → 定義 → 有効性…』
こんな感じで論点が流れていきますが、解答骨子を作らずに思いつきで書きだすと、
『有効性 → 上位概念 → 定義…』
という話がアチコチに飛んでしまい、話が繋がらない・読みにくい答案になってしまう可能性が高くなります。
こういった答案では点数が乗ってきません。
論点漏れを防ぐため
答案構成をせずにいきなり論文を書きだすと、かなりの確率で論点漏れ(書き忘れ)が出てきます。
本来解けた論点、拾えた点であれば非常にもったいないです。
合否のボーダーラインには何人何十人といてます。1点に泣く人もたくさんいます。
うっかりミスで点数を落とすことのないようにするためにも、答案構成をしましょう。
やり直しを防ぐため
上の『解答の流れ』や『論点漏れ』とも関連しますが、やり直しを防ぐためにも答案構成が必要です。
書くべきところに書かないと点数はつきません。
論文はボールペンで書く以上、大幅な修正はできません。
また修正したとしても、大量の二重線は見栄えが悪く採点者の印象が悪くなります。
書き忘れに気付いて、後から書いて矢印でグイーっと引っ張って挿入するような答案が見られますが、本試験で点数が乗っているのか詳細は不明です(1つ位なら大目に見てくれているかもしれませんが、2回も3回も続いていると多分×)
そもそも限られた試験時間のため、修正時間すらもったいないです。
「アレをここに書くの忘れてた!」を防ぐためにも答案構成は重要です。
加点事由を見つけるため(中級者以上)
論文試験では、問いに対する直撃の解答以外に補足的な解答を書ける場合があります。
加点事由と呼ばれているものです。
これが書けるとライバルから一歩抜きんでることが出来て、合格にグッと近づきます。
例えば…
- 総論1章の鑑定評価の責務の問題で、各論3章の責務まで触れることができれば加点
- 総論5章の問題で、基本的事項の確定は総論9章の鑑定評価報告書の必要的記載事項であることができれば加点
こんな感じで、解答例にないことを書いても点数が乗る可能性があります。
但し、加点事由で気を付けたいことがあります。
それは書きすぎないようにすること。
1つ隣の論点までしか加点は来ないと思っておいた方が良いです。
上の総論5章の例で言えば、『基本的事項は、鑑定評価報告書に書かなければならない』ということが書ければ加点が来る可能性が高いです。
一方で『鑑定評価報告書とは~』といった鑑定評価報告書の定義の論点まで書いても印象が悪くなるだけで加点にはなりません。隣の隣の論点だからです。
加点を狙うときは、『1つ隣の論点まで』と覚えておきましょう。
答案のボリュームチェック(中級者以上)
勉強が進み暗記量が増えてくると、加点事由も書けるようになって解答用紙2枚じゃ収まらなくなってきます。
何を書いて・何を書かないかを考えておかないと、論点に対する直撃の解答を書くスペースが足りなくなることも起こります。
答案構成の段階で書きすぎにならないかチェックしておきましょう。
暗記は答案構成ができるように行う
最初のうちは、いざ答案構成をしてみるとペンが動かないということが多々あります。
その原因は大きく3つです。
- 鑑定理論の理解不足でそもそもの問いの意味がわからない。
- 暗記できていないから解答が出てこない。
- 暗記しているはずなのに解答が出てこない。
それでは、解決方法を見ていきましょう。
鑑定理論の理解不足でそもそもの問いの意味がわからない
この場合、いくら悩んでも答えは出てきません。
悩む時間がもったいないので、すぐに解答例を見て鑑定理論の理解を深めましょう。
解答例を見ておおよそ理解ができたら、
- もう一度同じ問題で答案構成をしてみる。
- 類題を解いてみる。
これで理解の確認、定着を図りましょう。
暗記できていないから解答が出てこない
暗記不足です。
インプット3割、アウトプット7割を目安に進めるべきですが、まずは最低限の暗記は必要です。
暗記しているはずなのに解答が出てこない
一番アルアルな現象です。
これは暗記の仕方に問題があります。
主な原因は2つです。
- 覚えているものの意味が理解できていない。
- 覚えているものにラベルが付いていない。
ただ覚えているだけの棒暗記になっていたり、せっかく暗記してもラベルがついていないので、整理ができていない状態です。
インプットはアウトプット出来てこそ意味があります。
暗記する段階で、
“再調達原価の定義”
“置換原価の定義”
“再調達原価(建物)の求め方”
“再調達原価(土地)の求め方”
“再調達原価(建物及びその敷地)の求め方”
こんな感じでラベルを付けておく必要があります。
ラベル付けは超重要なので絶対やるようにしてください。
長くなってきたので、いったんここで終了します。
この記事のおさらい
- 答案構成とは、解答の道筋を作る作業
- 答案構成の必要性
- インプットは答案構成をできるように意識して行う。
答案構成の必要性や、答案構成の準備段階としてのインプットの仕方を紹介しました。
次回は具体的な答案構成のやり方についてお話していきます!